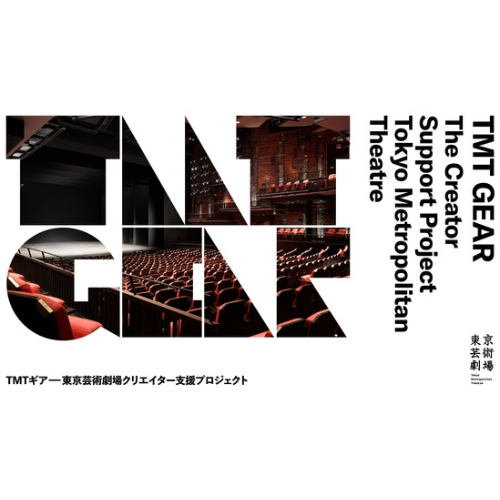当サイトでは、サイトの利便性向上のため、クッキー(Cookie)を使用しています。サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、「プライバシーポリシー」をお読みください。
東京芸術劇場 芸劇舞台芸術アカデミー シアター・コーディネーター養成講座
「“当事者”って誰だろう?――リサーチから舞台芸術を⽴ち上げる――」
実施レポート
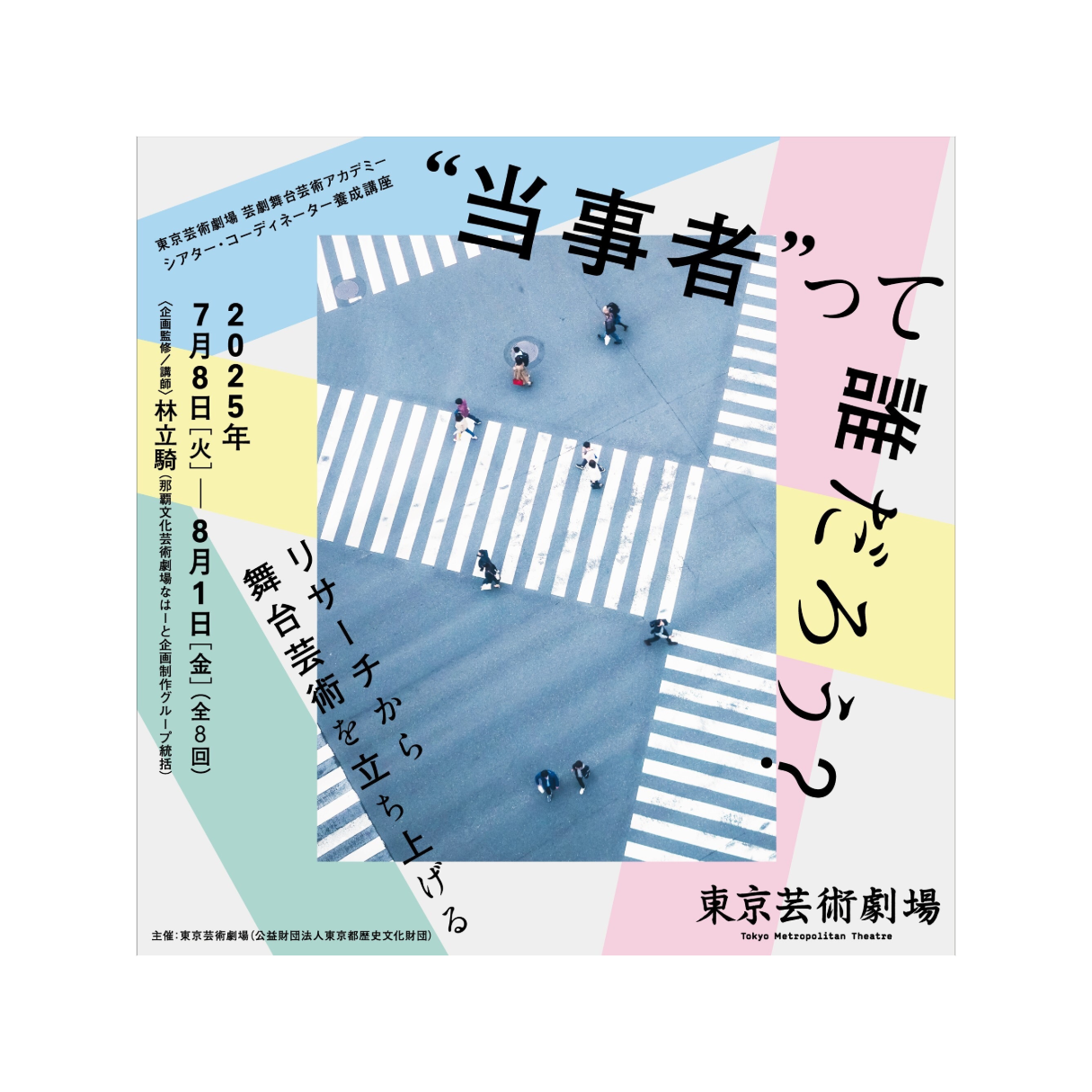
劇場と社会の間に立って、両者をつなぐ企画を考え、調整、発信する人材の育成を目指す、東京芸術劇場「シアター・コーディネーター養成講座」。2019年よりスタートし、様々なテーマで開講しています。
今回は「“当事者”って誰だろう?――リサーチから舞台芸術を立ち上げる――」と題し、「当事者」や「リサーチ」をキーワードに、監修・講師に林立騎さんを迎えてフィールドワークや対話、レクチャーなど様々な形式の中で学んでまいりました。
本稿では、講座内で実施したフィールドワークの様子を写真とともに振り返ります。
7/14(月)フィールドワーク① 東京地方裁判所
【東京地方裁判所前に集合】
この日、多くの受講者が初めて訪れた東京地方裁判所。入場には荷物検査が必要です。1階ロビーには当日開催される裁判が検索できるタッチパネルが設置され、来訪者は自由に閲覧できます。
【傍聴した裁判は2件】
当初は「出入国管理及び難民認定法違反」の裁判を1件傍聴する予定でしたが、その場の傍聴人数に余裕があったため、2件の裁判を傍聴しました。
1件目の裁判では違法薬物を国内へ持ち込んだ被告人への判決、2件目の裁判では外国人技能実習制度の適用で来日した後、不法滞在となった被告人への判決が言い渡される瞬間を、傍聴席から目の当たりにしました。限られた時間ではありましたが、いずれの被告人も非日本語話者だったことから、法廷通訳人が通訳を行う様子も見ることができました。
【会議室に移動し、ディスカッション】
東京地方裁判所を後にし、休憩を挟んで会議室に再集合。互いの感想や気づきをシェアし合う時間を持ちました。
裁判官の振る舞いや話し方、傍聴席に届かない声のボリューム。また、検察官の強硬とも思える態度への驚きや違和感。法廷通訳人の役割の大きさや、通訳内容がその言語の話者以外には正確なものなのか判断ができないのでは?という疑問。法廷と劇場の構造的な類似点。傍聴席で傍聴する人が抱き得る被告人への好奇心と後ろめたさ、傍聴人が持つ暴力性とともに、目撃者として法廷に与え得る影響についても話が及びました。

7/23(水)フィールドワーク② 領土・主権展示館
【領土・主権展示館に集合】
領土・主権展示館は、特に北方領土・竹島・尖閣諸島に関する発信拠点として2018年に開館した虎ノ門にある国立の展示施設です。運営は内閣官房 領土・主権対策企画調整室が行っています。この日、受講者全員が初めて本施設を訪れました。
【解説員による展示解説】

2グループに分かれ、元内閣府に務めていらっしゃった解説員のもと、北方領土・竹島・尖閣諸島の各ブースでパネルや短編動画、展示品を見ながら各島々の歴史や現状について基本的な知識を学びました。
2025年4月のリニューアルオープンで新たに追加されたのが、「イマーシブ・シアター」をはじめとする大型の映像を使用した展示コーナー。北方領土・竹島・尖閣諸島の自然の美しさや豊かさを訴求するのに一役買っていた一方で、スペース確保のためにいくつかの展示を取り下げたそうです。取り下げられたものの中には、諸外国から各領土問題を見たときの「各国の主張」に関する展示が含まれていたと聞きます。

【会議室に移動し、ディスカッション】
前回同様、休憩を挟み会議室に再集合し、ディスカッションを行いました。
スペース上の問題で「各国の主張」に関する展示を取り下げたという話から、来館者が様々な情報から領土問題について考えを深めるということよりも、「分かりやすさ」や映像体験を優先しているのではないか?という疑問や、配布用パンフレットの言語設定(英、中、露、韓)と実際に来館する外国の方々との相関関係など、実際に訪れて解説を聞いたことで浮かび上がった様々な問いや気づきが共有されました。
自らの目や耳で体験することなしに実感を持つことの難しさを再認識した計2回のフィールドワーク。「自分では知らなかった、あるいは行かなかった場所だった」という声も度々聞かれました。今回の体験が「当事者」という言葉のイメージを広げる契機となるとともに、個人の体験としても、それぞれの企画を練り上げる上でも、有意義な時間であったことを願っています。
最終回で話された、監修者の林立騎さんからの言葉

受講者それぞれが企画発表を行った講座の最終回。この日は見学で来てくださった豪華ゲストの方々からも企画へのコメントをいただくなど、大変充実した2時間となりました。
本レポートの締めくくりとして、監修者の林立騎さんがこれまでの講座を振り返って話されたお話から、一部を紹介したいと思います。
「私自身は本講座から大きく3つのことを学んだように思います。1つ目に、現在の社会の構造的な問題や歴史上、そして今も続く個人の苦しみを学ぶことは大切だということ。
2つ目に、他者のみを当事者とするのではなく、そのことをこれまで学んでこなかった自分や、今その問題を語らせようとしている自分とは何なのか?という自己の当事者性、自己批評性、自分自身と現在の構造を変化させることが重要だということ。
最後に、舞台芸術に関わるものとして、作品という枠の内外のどのような時間性と身体性において継続的に取り組むかということです。
私はやはり良い作品や良いプロジェクトこそが大切だと思います。そして、良いという言葉を、観客や参加者、個人の経験と現在の社会構造の両方をより自由に寛容で公正な方向へと変化させるという意味で捉えたいと思います。
参加者や観客と共に、どのような時間のなかでどのような場や身体的な感覚を共有していくかということが、他者と共にある時間芸術としての舞台芸術にとって重要なことのように思います。」
■講座概要
東京芸術劇場 芸劇舞台芸術アカデミー
シアター・コーディネーター養成講座
「“当事者”って誰だろう?――リサーチから舞台芸術を⽴ち上げる――」
期間:2025年7月8日 (火) ~2025年8月1日 (金)(全8回)
ゼミ①「オリエンテーション」
レクチャー①「ドキュメンタリー演劇をつくるプロセス」(一般公開/オンライン)ゲスト:村川拓也(演出家・映像作家)
ゼミ②「対話の時間(1)」ゲスト:村川拓也(演出家・映像作家)
ゼミ③「劇場と社会のあいだのフィールドワーク(1)」
レクチャー②「“当事者”って誰だろう?〜沖縄の実践者と考える〜」(一般公開/オンライン)ゲスト:兼島拓也(劇作家)、石垣綾音(まちづくりファシリテーター)
ゼミ④「劇場と社会のあいだのフィールドワーク(2)」
ゼミ⑤「対話の時間(2)」ゲスト:温又柔(⼩説家)
ゼミ⑥「企画発表&フィードバック」
会場:IKE・Biz としま産業振興プラザ、新宿NPO協働推進センター、都内各所
(フィールドワーク) ほか
企画監修/講師:林立騎(那覇文化芸術劇場なはーと企画制作グループ統括)
主催:東京芸術劇場(公益財団法人東京都歴史文化財団)